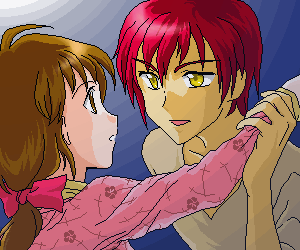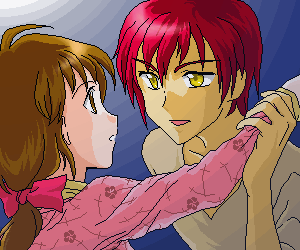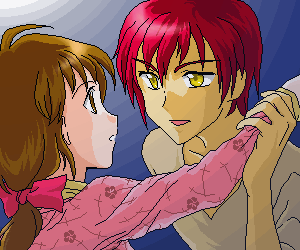 |
「ねぇ、姫…?」
ぞくりと、其の声だけでどうにかなってしまいそうだ。
艶のある男の声、女の子のように整った顔立ちなのに其の声はどこまでも『男』で、私の『女』の部分が強く刺激される。
あんなに細いと思っていた手に腕がつかまれて、どうしてか、自分の腕が脆く壊れやすいもののように感じてしまい、其処だけが熱を持ったように熱い。
金色の瞳は、薄暗闇の中、妙に妖しい。
視線で囚われてしまったかのように、私の体は動くことを忘れていた。
「姫君のことだから、分かってないんだろうけど。」
とんっと、背中が壁にぶつかる。
どうして、なんで。
連君の顔が、近い。
唇が彼の吐息を感じるほどに、金色の瞳がダイレクトに私の瞳を覗き込むほどに近い。
呼吸がはねる、心臓の音はうるさいくらいで、連君に聞こえてしまわないかと唇が緊張を覚える。心臓が飛び出てきてしまいそう、だなんて、きゅっと慌てて結んで。
熱い。
暗くてよかったとふと思った。
自分でもわかるほどに熱を持った頬は見るも無残なほどに赤いだろう、それを彼に見られたならばきっと恥ずかしさで私は死んでしまう。
きゅっと私の腕を掴む連君の手に僅かに力がこもった。どうしよう、そこから、熱が伝わってきて、そして連君にまで伝わってしまいそうで。
「誘ってるわけ?」
やめて、耳元で、囁かないで…
甘い吐息が耳たぶにかかり、艶っぽい声が聴覚神経に針を刺したんじゃないかと思うくらいに体中に響き渡る。
「本当、姫さんは可愛いね…?」
唇が笑っているのだけが見える。
腰に手が回されたことなんて、もう気にならないくらいに私の頭は、パンク寸前。
どうにか、なってしまいそうだ…
「―――――なんてね。」
「……へ?」
不意に、金色の瞳の中にあった色香が、ふと消えた。
私を捕らえていた手が離され、開放される。声はいつもの、どこか悪戯っぽい声に戻っており、口元も楽しげに笑っていた。
―――いつもの、連君だ…
「ふふっ、からかってごめんよ姫君。でも、中々に可愛くって食べちゃいたいくらいだったけど、ね?」
ふわりと頭を撫でられる。
やはり、男の子の手だ、意識したことなどなかったけれどあの後では否が応でも意識せざるを得ない。
弓を使う者らしい、細く、しかし硬い指。
緊張の糸が切れたようだった。
体中の力が抜けてその場に座り込む。廊下から入ってくる光が連君の顔を照らして、彼が私をいじめるときの表情をしていることが見えて、なんだか、妙に悔しくて。
「本当に可愛いね。」
「……連君の意地悪…」
からかわれていたのならばいい。
そう、いいの。
残念だなんて思うこの心は、きっと、嘘っぱちだから。
なのに。
「安心しなよ、俺は本当に好きな女は大事にするタイプでね。」
去り際に、見たことがないくらいに優しい笑顔に、穏やかな声。
それって――――――反則。
|
|